今年の正月休みは、1月4日までですが、急用の場合はいつでも連絡OKです。
行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について
行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について
日本行政書士会連合会
会長 宮本 重則
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。改正法の施行まで2か月となり、あらためて改正後の行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第19条第1項(業務の制限規定の趣旨の明確化)及び第23条の3(両罰規定の整備)の趣旨等についてお知らせし、関係各位のご理解を賜りたいと存じます。
まず初めに、改正法により法第19条第1項の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられました。
この改正は、コロナ禍において、行政書士又は行政書士法人でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことから、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは、法第19条第1項に違反することが明確化されたもので、これらは現行法においても変わりはなく、改正法の施行日前であってもこうした行為があれば同条に違反することになります。
次に、改正法により法第23条の3の両罰規定に、行政書士又は行政書士法人でない者による法第19条第1項の業務の制限違反に対する罰則が加えられ、違反行為者が罰せられることはもとより、その者が所属する法人に対しても百万円以下の罰金刑が科せられることとされました。
当会といたしましては、これらの改正趣旨を踏まえ、行政書士又は行政書士法人でない者による違反事案に対して、関係機関とも連携のうえ厳正に対処し、もって国民の権利利益の実現に資することとしておりますので、今後もご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
行政書士法の一部を改正する法律案要綱
行政書士法の一部を改正する法律案要綱
一 行政書士の使命
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与すると
ともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とす
るものとすること。
(第1条関係)
二 職責
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公
正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、
情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の
改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
(新第1条の2関係)
三 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手
続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書
士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政
書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
ものに拡大すること。
(新第1条の4第1項第2号関係)
四 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受
けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に
すること。
(第19条第1項関係)
五 両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限
違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両
罰規定を整備すること。
(第23条の3関係)
六 施行期日等
1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
相続した売れない土地があれば当方にご相談下さい。
「相続したものの使い道に困る土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月に創設されてからの1年半余で、長野県内で国有化された土地は申請の3割弱にとどまる。法務局の審査を通れば一定の負担金を納めることで国に引き渡せるが、更地でなければならないなど多岐にわたる要件を満たせず、申請そのものを断念する例も多いのが実態だ。」
相続土地国庫帰属制度 とは、相続(または遺贈)したものの不要で、かつ、売却しようにも買い手の付かない土地である場合に、当該制度を利用して国に買い取ってもらうというもの。
当該制度を利用する場合は、当該土地を管轄する最寄の法務局に承認申請が必要で、申請の前位には要件を満たす必要があります・・
①更地であること、つまり、建物は解体除去しなければならない。
②担保権や使用収益権は抹消しなければならない。
③他人の利用が事前に決まってる土地は不可。
④土壌汚染のある場合は不可。
⑤境界を明らかにする必要があり、紛争なきこと。
⑥一定の勾配・高さの崖があり、相応の管理費用がかかることが予想される土地。
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地。
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地。
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地。
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
以上、①~⑩のないまっさらな更地にしないと国は買ってくれませんので、申請のためには要件を満たすべく事前の作業が必要になりますね。
原則論として、申請は本人申請が基本ですが、申請を行政書士が専門家としてお手伝いできますので、当事務所にご相談下さい。
夏季休暇のお知らせ。
8月10日(土)から8月15日(木) 当事務所は夏季休暇となります。
今年の新しいポスターが完成しました・・
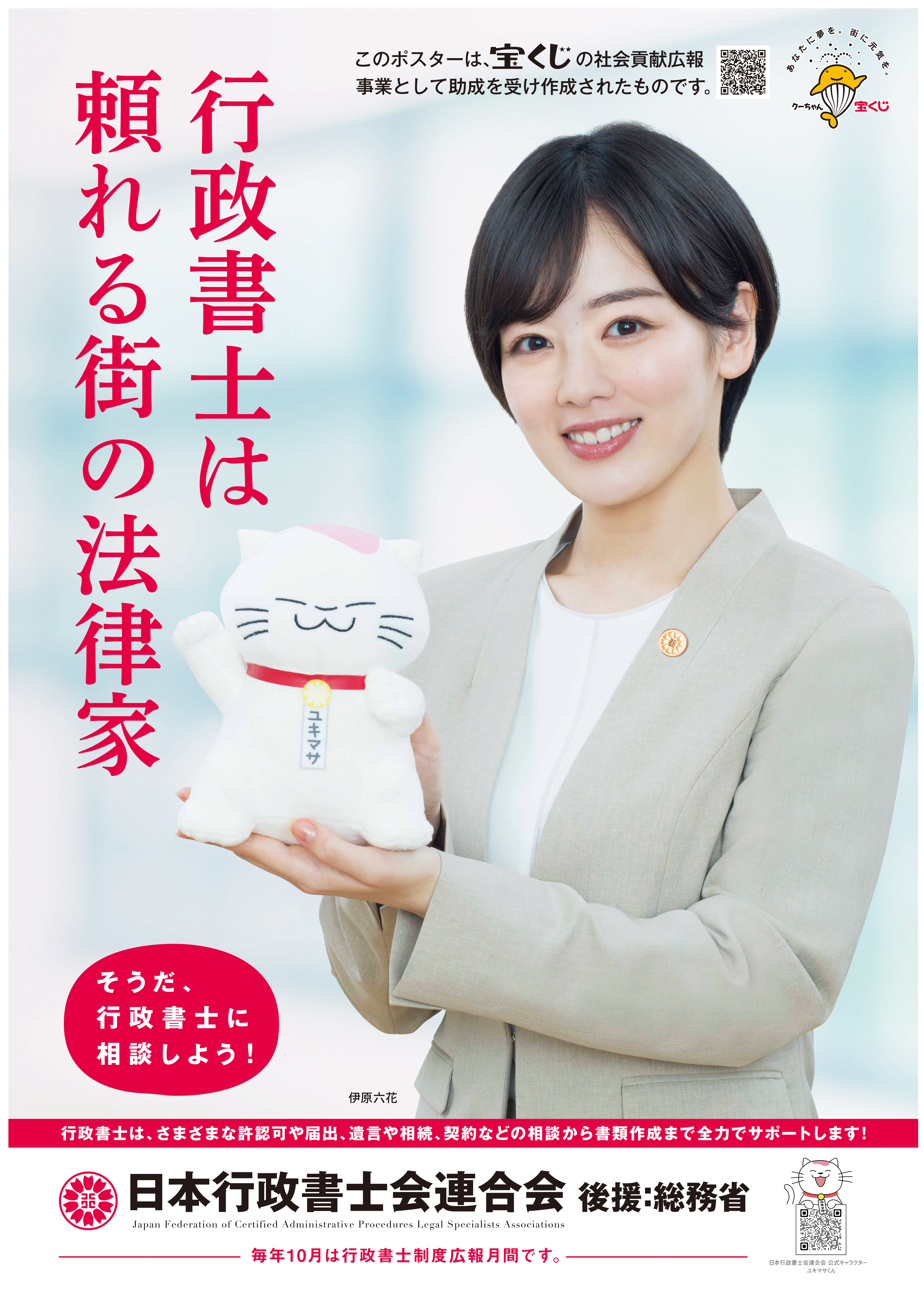
デジタル庁と日本行政書士会連合会が連携協定を締結
デジタル庁と日本行政書士会連合会が連携協定を締結デジタル庁と日本行政書士会連合会は、「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために必要な事業の企画及び実施に関して、連携協定書を締結することとしました。河野太郎デジタル大臣、大串正樹副大臣、当会の常住豊会長らが出席し、令和5年9月1日デジタル庁にて署名式が開催されました。==========「デジタル庁と日本行政書士会連合会との連携協定書」デジタル庁(以下「甲」)及び日本行政書士会連合会(以下「乙」)は、「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために必要な事業の企画及び実施に関し、相互に協力して推進するため、次のとおり合意する。各種行政手続のオンライン化・デジタル化に際しては、手続処理の迅速化が当然の前提となる。そのためには、国民、事業者を問わず添付書類の簡素化、省略化及び代替化並びにそれらを踏まえた行政側での審査の簡素化等が欠かせない。また、国民に関しては、マイナンバーカードによる本人確認サービスの利用が想定されているが、事業者の手続に関しては、現状でも多種多様な資料添付が求められるものもあり、この簡素化・円滑化にデジタル庁を始めとする行政側は取り組んでいく必要がある。一方、公正かつ適切な行政の執行のためには、簡素化・円滑化の前提として申請内容の真正性が確保されなければならない。この点において、適正な行政手続の実施により国民の権利利益の実現を担う、全国5万2千人もの地域に根ざした法律の専門家である行政書士の力が大変重要であり、行政側と行政書士の両者による我が国の行政及び社会のオンライン化・デジタル化に向けて、甲と乙は、次の取組を協力して行う。1 甲は、次項に定める乙の取組に対して、乙の求めに応じて必要な協力を行う。2 乙は、行政書士業務の特徴である広範性と補完性を活用し、また、行政手続及び権利義務・事実証明に関する書類作成を業とする専門家として、次の活動を行う。(1)マイナンバーカードの普及促進(2)政府及び地方自治体が推進する行政手続のオンライン化・デジタル化による手続処理の迅速化・円滑化の推進と適切かつ公正な行政事務遂行の確保(3)行政手続のオンライン化・デジタル化の推進に伴う検討及び行政側との情報共有(4)小規模事業者、高齢者、障がい者、外国人等に対する行政手続のオンライン化・デジタル化の普及促進(5)その他甲が企画推進し、乙としても推進すべきと判断した事業に対する、乙から甲への協力3 甲及び乙は、上記1及び2の取組に当たり必要と認める場合には、いずれかからの申出により、随時に協議を行うこととする。4 以上の取組に関する詳細については、これを別に定める。
行政書士は頼れる街の法律家・・

今年のポスターは・・モデルは変更ぜず継続なのか。
昨年度は、「そうだ、行政書士に相談しよう」だったのですが、
また、法律家が復活したのですかね・・
一部の弁護士会は行政書士が法律家を自称することに反対してますが・・
成年後見業務は行政書士の業務であることの再確認
「行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1 条の 2 及び第1条の 3 第 1 項
(第 2 号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人
等業務」は、行政書士法第 13 条の 6 第 1 号・行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号に
規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。」
成年後見業務は正式に行政書士の業務であることが総務省により再確認されました。
相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日からスタートします。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
申立のご希望のある方は、当事務所にご相談ください。
